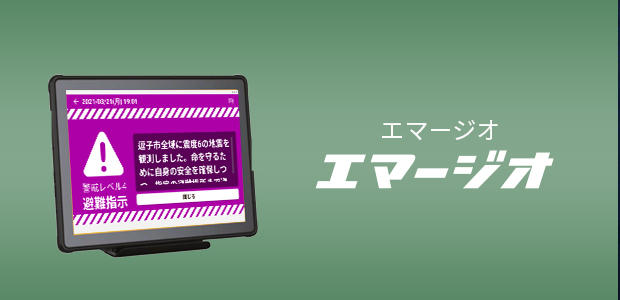災害は皆同じ。被害はあなたの備え次第。
テレネット株式会社は
防災対策のエキスパートとして、
皆様の安全・安心対策をサポートいたします。
~令和6年能登半島地震における
通信サービスの支援措置~
当社の通信サービスを必要とされる被災地のお客様に、
以下の当社製品の貸出を行いました。
製品・サービスご活用状況はこちら
お知らせ一覧を見る 〉
- 2024年4月24日
- 第20回オフィス防災EXPO(東京 2024年5月8日〜10日開催)に出展します
- 2024年4月19日
- [速報] 2024年4月17日に発生した豊後水道を震源とする地震時の「ハザードプロ」配信状況ご報告
- 2024年4月18日
- [速報] 2024年4月17日に発生した豊後水道を震源とする地震時のDEWS配信状況ご報告
イベント・セミナー情報一覧を見る 〉
- 2024年4月24日
- 第20回オフィス防災EXPO(東京 2024年5月8日〜10日開催)に出展します
- 2024年1月26日
- 第28回震災対策技術展(横浜 2024年2月8日〜9日開催)に出展します
- 2024年1月16日
- 「第10回ウェアラブルEXPO」(2024年1月24日~26日開催)に出展します
知っ得!防災知識
防災対策のエキスパート、
テレネット株式会社だからお届けできる
最新の防災情報や事例などの
お役立ち情報をコラムでご紹介
-

2024年3月27日
光回線の通信障害は日常的に発生している!
企業・団体活動に与える影響や備えなどを解説 -

2023年12月12日
衛星電話とは?特徴とメリット・デメリット、使用方法などを解説
-

2023年9月1日
【9月1日は防災の日】関東大震災から100年
二度と繰り返さないための企業・団体の防災対策 -

2023年1月26日
MCA無線とは?特徴を解説